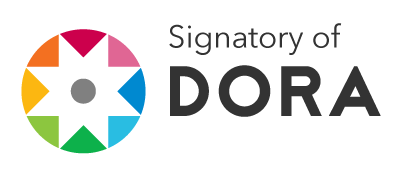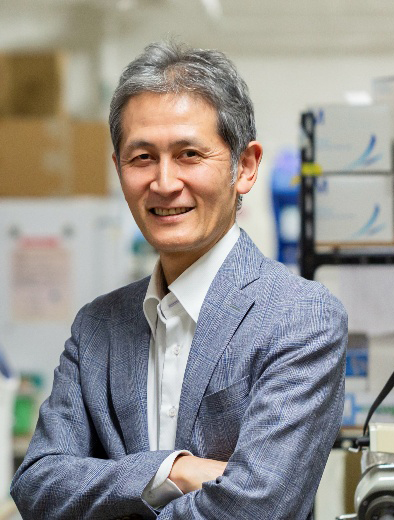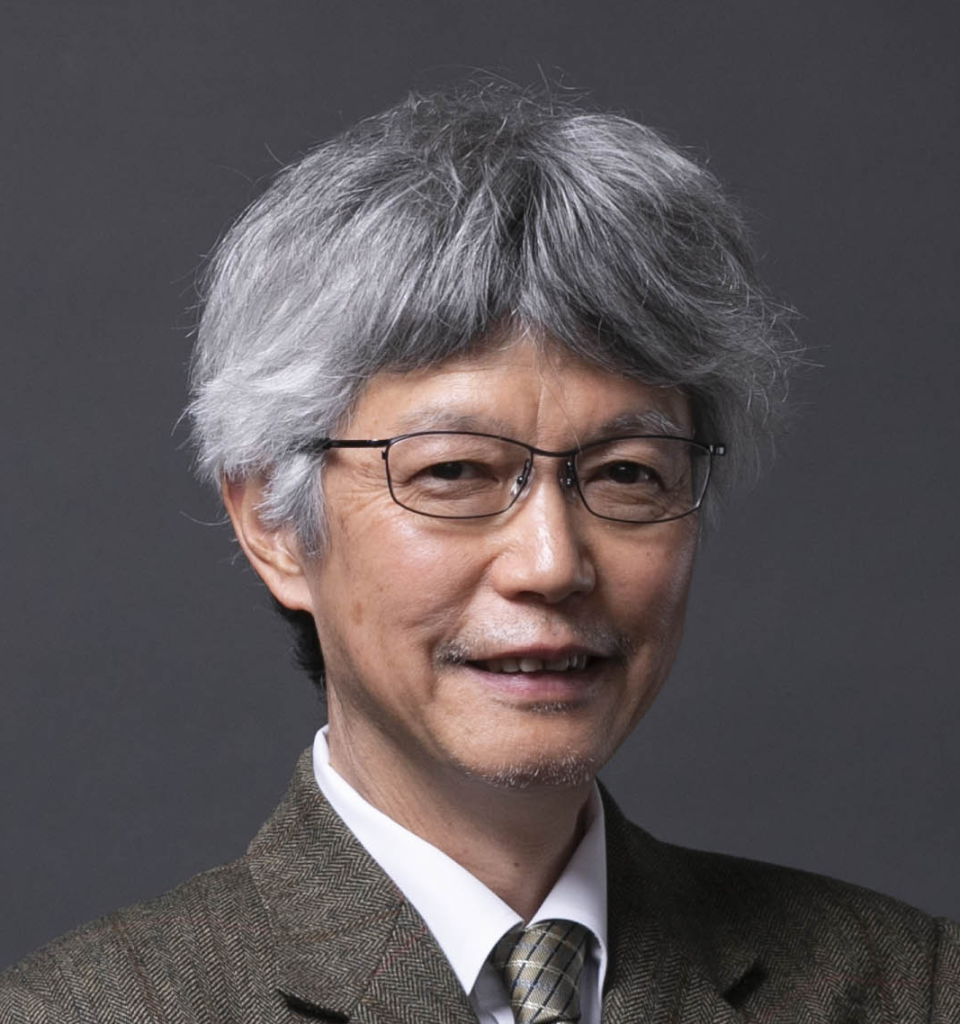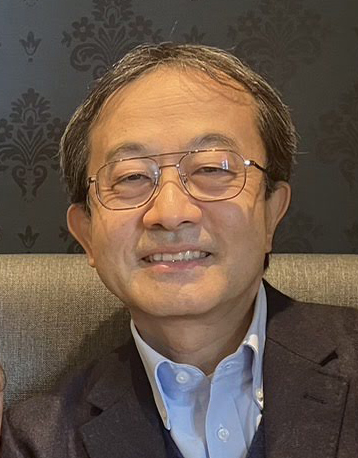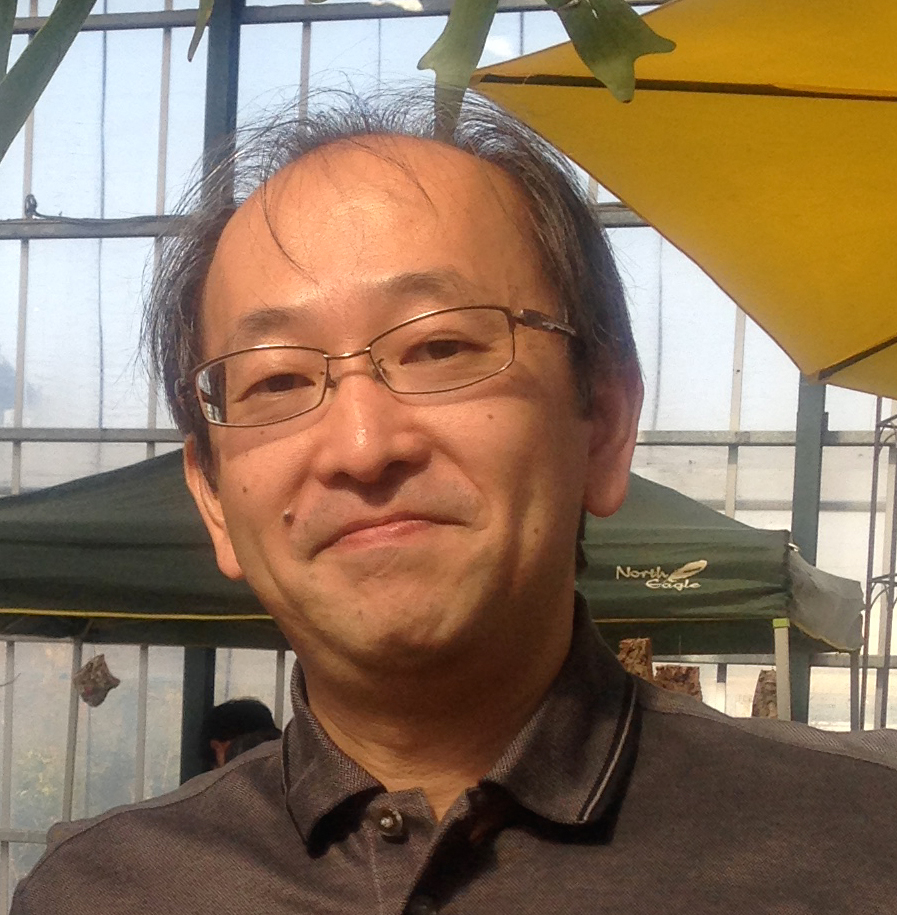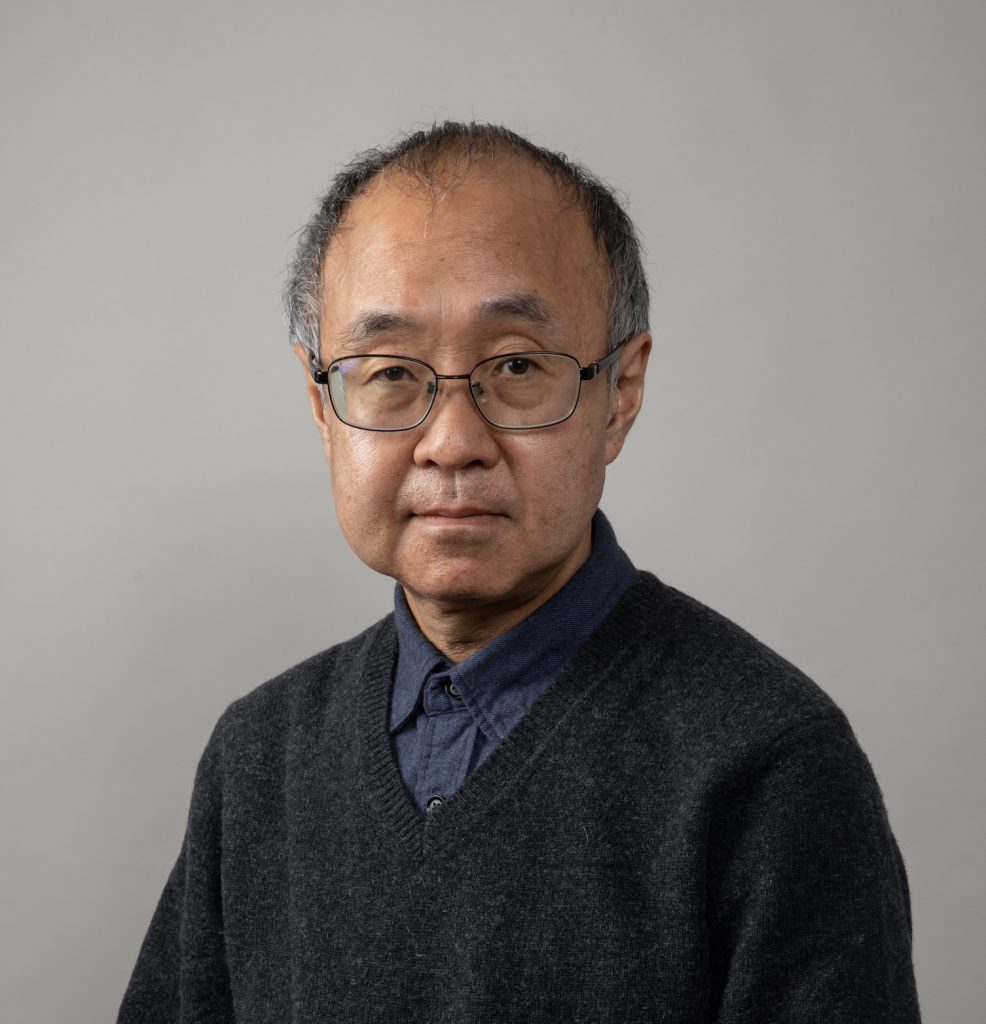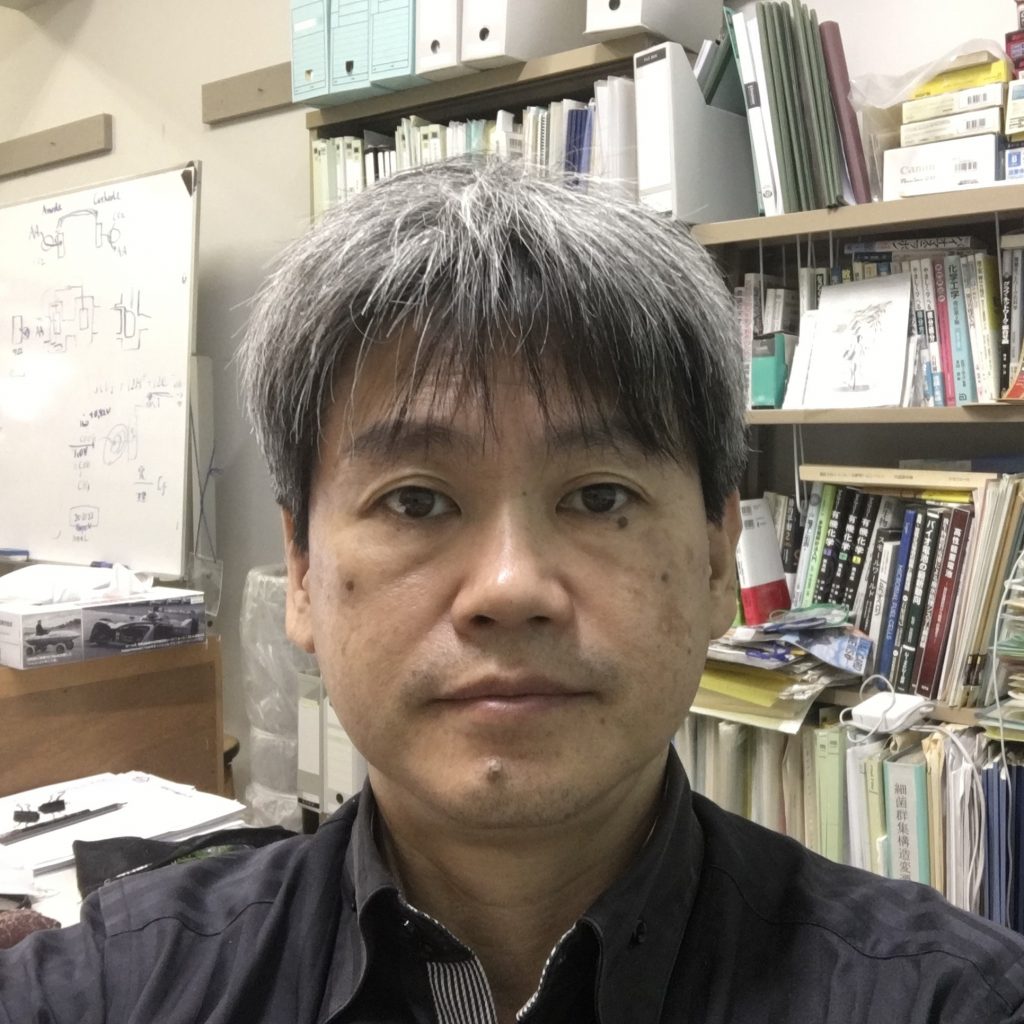第1条
本連合は会員の活動に関する情報連絡の便宜を図り、必要に応じ連合として意 見を公表し、生物科学の発展並びに普及に務めることを目的とする。
第2条
会員は生物科学に関連する学術学会で、この連合の目的に賛同する団体とする。
第3条
本連合は毎年1回以上の定例会議を開催する。また、代表が必要と認めたとき、 あるいは会員の1/3以上の要求があったときに臨時会議を開催する。
第4条
本連合の会議には、各学会の学会長またはその意志決定を代行しうる立場の会員による代理人が出席するものとする。また、会員としての議決権を付与しないで以下の者の参加を求める。日本学術会議の基礎生物学・統合生物学・基礎医学の各分野別委員長、国際生物学オリンピック日本委員会委員長、本連合前代表および本連合が必要と認めた者。
第5条
本連合には、1名の代表をおく。代表は会員の推薦による候補者の中から会員の互選により選出され、連合の運営にあたる。代表の任期は2年とし、重任は1回に限り認め、再任は妨げない。選出については細則にて別途定める。
第6条
本連合には、1ないし2名の副代表をおき、代表の職務を補佐する。副代表は代表が推薦し、会議で承認されるものとする。副代表の任期は2年とし、再任は1回に限り認める。
第7条
本連合には、本連合の迅速な意志決定を行うために、代表の諮問に応ずる運営 委員会を置く。運営委員会は代表・副代表を含め6名以内の運営委員により構成し、 運営委員は代表が推薦し、会議で承認されるものとする。運営委員の任期は2年と する。ただし代表任期の中途で新たに運営委員が選出された場合、その任期満了は 代表に準じるものとする。
第8条
本連合への入会は、所定の入会申込書(別添)に必要事項を記入して代表に提出する。代表は全会員に可否を諮り、過半数の会員の賛同が確認された場合に承認される。
第9条
本規約は定例会議で総会員の2/3以上の賛同をもって改正することができる。
第10条
議決は定例会議において書面委任を含む総会員の2/3以上の賛同があれば成立する。ただし、議決案件については会議開催の2週間前までに各会員に通知しなければならない。
第11条
意見の公表は、文書により行い、ホームページ、当事者・報道機関への送付、記者会見等により行う。
第12条
議決の要件が整わないが、代表が緊急に必要と認めるときは、運営委員全員の賛同もしくは会員の過半数の書面または電子的書面による賛成をもって、生物科学学会連合緊急声明をだすことができる。
第13条
会員は本連合の運営費として、年額50,000円を納める。2年間滞納した会員は会議で議決の上、除名することができる。
付則
1)連合の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
2)運営費は事務局で管理し、定例会議等の開催経費やホームページ維持管理費用等の恒常的な運営経費および本連合の目的達成のために使用する。
3)本連合には2名の会計監査委員をおく。会員の互選により選出し任期は2年とする。監査委員は年度始めの定例会議にて前年度の監査報告を行う。
4)本連合相互の連絡等に関する事務局は、中西印刷株式会社内におく。
5)本規約は2015年3月7日より発効する。
代表選出議決細則
1.代表は会員学会の所属であり、会員学会から推薦された候補者から、会議の議決により決定する。
2.会議の代表選出議決にあたっては各会員が1個の議決権をもつ。議決権の行使に当たっては規約第4条の資格を有する者に限る。ただし書面または電子書面による委任または事前投票を妨げない。
3.会員学会は複数の候補者を推薦することはできない。
4.代表選出は前代表任期満了前6ヶ月以内に行う。
5.選出の公示は選出前2ヶ月以前に書面または電子書面にて行う。
6.各学会の候補推薦届け出は選出を議題とする会議2週間前までに各学会が現代表に対して候補者名と趣意を書面または電子書面で表明することで行う。代表は候補推薦をただちに書面又は電子書面にて各会員に通知する。
7.推薦候補者が1名に限られる場合、議決を経ず、該当候補者が代表に選出される。
8.代表選出議決にあたって、書面・電子書面での委任・事前投票も含め、総会員の過半数の賛同を得た者を代表に選出する。過半数に達しない場合は上位2者で再度選出議決を行う。
9.再選出議決において、なお賛同が総会員の過半数に達しない場合は、書面・電子書面での委任及び事前投票及び出席者による投票数合計の過半数において決する。なお同数の場合は代表が決する。
10. 本細則の改正は規約の改正規程に準ずる。
事前投票取り扱い細則
1.書面・電子書面委任による事前投票の場合、第一希望と第二希望を記載することができる。
2.事前投票は一回目の投票においては第一希望者に投票したものとみなす。
3.二回目の投票において、第一希望とした者が上位二者にある場合は、第一希望者に投票し たものとみなし、ない場合は第二希望者に投票したものとみなす。二回目の投票において 第一希望・第二希望とも候補とならない場合は棄権したものとみなし、投票数には繰り入れない。